◎ 自分が将来 受取れる年金は いくら?
年金に関して 個人情報(年金給付額等)の入手が便利に!!
| ● 社 会 保 険 庁 ● |
| ① 社会保険事務所で ”年金給付見込額の試算” をする際の対象年齢の引き下げ (従来は58歳から) |
| ◆ 年金給付見込額の試算 |
| 58歳~ | 55歳~ | 46歳~ |
| ② 被保険者記録 (平成16年3月から満58歳になると、それまでに支払った保険料の記録 <年金加入記録>) が通知される (58歳を迎えた翌々月以降) |
| ◆ 上記の通知の後、同封の返信ハガキで年金給付見込額希望を、社会保険庁に連絡 ⇒「年金給付見込額」 が通知される |
| ③ 社会保険事務所に行かなくても、順次 電話やインターネット等で 色々な情報が教えてもらえるようになる |
| ◆ 相談手段が多様化され、現在は通知へ (従来は、社会保険事務所に訪問) |
| 社会保険事務所に訪問 | 電話でも可能に インターネットで 加入期間など可能に | 保険料の納付実績 や給付額の目安を 定期的に通知 |
| ● 65歳で変わる厚生年金の仕組み (「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」) |
| ◆ 毎年、誕生月に 「年金受給権者現況届」 が郵送されてくるので記載して提出する |
| ◆ 65歳から変わる年金の種類 (誕生月の前月末に社会保険庁から郵送される) |
| 特別支給⇒の老齢厚生年金 |
|
【65歳~ 】
| |||||||
| (厚生年金保険の加入年齢の延長) |
| ◆ 60歳から65歳未満の人の ”在職老齢年金” は?(→) |
| ◆ 65歳から70歳未満 及び 70歳以上の人の ”在職老齢年金” は?(→) |
| については、標準報酬月額(賃金の額)に応じて、年金額の ”一部から全額” が支給停止となります。 |
☆ 年金受給は、死亡した月分まで貰える権利があります ☆ 原則 年6回で <偶数月に前2ヶ月分> が支払われる <例>12 ・1月分 → 2月に支給される ☆ 年金の『源泉徴収票』 は支払基準 (発生基準でなく) で作成されています 相続開始日以前のものを遺族が受給しても相続財産にはなりません 遺族の固有の権利で 「一時所得」 に該当 (所基通34-2) |
≪年金制度改革に戻る≫ ≪年金いつから受給?に戻る≫ ≪死亡後の手続きに戻る≫
年金額がいくら貰えるのか? は、社会保険庁の情報提供が充実され 知ることができる様になりましたので、プランが立て易くなりました。
但し 60歳以上の人で、会社から給料を貰っている場合には、その給料との兼ね合いで受取る年金額が異なってきます。
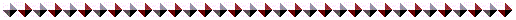
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/